特集02 小豆島のミライ ~島で営み続ける、ということ~ Carrying Life Forward on Shodoshima
- harayama0
- 2025年4月12日
- 読了時間: 3分

今回の「小豆島のミライ」では、
昨今注目されている“持続可能な観光地”を考えることからスタートしました。
資本を投下し回収と成長を未来永続させる命題から生まれた日本語にはなかった“持続可能”という言葉には
成長の臨界点は想定されず、永遠に成長維持継続=持続可能性を追及するための意味もあるからです。
ゆえに、「回収と成長」のための延命を求め、本質と実態が伴わないままの向き合いになる企業や自治体が出ることも
人の性(さが)として、決して賛同はしませんが、哀しく理解できたりもします。
翻って、現実。
自然は、人間の経済なんてお構いなしです。
全ての命は、必ず終わりを迎えます。当然、持続はできません。
しかし、死んだとて、何事もなかったように、自然は営み続けます。
次の種または世代に、空間的にも、その席を譲るという理です。
では、「人の暮らし」はどうでしょうか?
不幸にも自然のいたずらひとつで、人の営み・暮らしはひとたまりもないことは今も昔も同じです。
それでも、人は目の前の自然の恵みを享受し、そこに住み、次へバトンを渡し、暮らしと営みを続けてきたことは、目の前に広がる棚田、小豆島八十八ヶ所霊場、農村歌舞伎などがまさに証左です。
この島で営みが続いてきたのには、そこには、人がつながり、ミライへの意志と想像力があるからです。
今回インタビューをした小豆島町商工観光課 片岡琴未さんは、ミライへの意志と想像力をこう言葉にして話してくれました。
「私は生まれてこの方、小豆島を嫌いになったことがなくて、他に選択肢はないほどに、世界一いいところだと思っています。周りを見たら誰一人、同級生がいなくなっていたことがあっても、出て行こう、と思ったことはありません。今、私のような存在はなかなか貴重なんです。もし、島から離れたとしても将来の選択肢として、郷土に自信を持って“当然、島に帰るやろ”と素直に言える子らが、この島に、いっぱいになってほしいなあ、と思います。それが当たり前に思える人たちが、もっと増えるようにしていくのが、島の行政をはじめ、観光分野に携わっている人間の今やらないといけないことだ、と思っています」
愛する豊かな土地で、営み続けること。
自然の恩恵と、人のつながりと暮らしから生まれる文化が、島の観光の基盤です。
自然、暮らし、文化は古くなったからと言って使い捨てて、新しいものを買ってくることもできません。
永く付き合い使えば、確実に育っていきます。
もし傷んできたら、暮らしと営みを続けていくため、自分たちの未来のつながりを想像し、
繋がりを紡ぎなおして再生させること。再び新しい命を吹き込むこと。
これは明日だけの為の経済的なモノサシだけでは、とても割に合わないかもしれない作業です。
しかし10年後、20年後を見通し意志と未来への想像力を持った人たちの、地に足をつけて舞台袖から支えている後姿が、取材を通じて見えてきました。 (小豆島倶楽部 2025 春夏号 「小豆島のミライ」冒頭より)

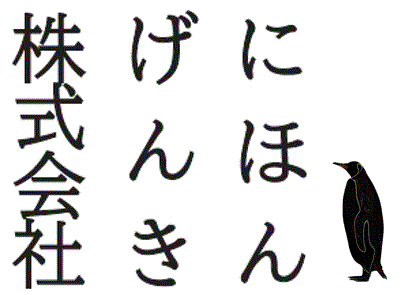



コメント